山梨県にある早川町。
日本で一番人口が少ないといわれている。
南アルプスの麓に位置し、中央付近には町の由来である早川が流れていて、自然豊かな町です。
今回は早川町の北側にある、
一般車両が行ける終着点にある集落の『奈良田』を中心に
かつては鉱山などで賑わいをみせた『茂倉の里山』
重要伝統的建造物群保存地区に指定されている『赤沢宿』などを
散策してきましたので、その中のおすすめのエリアを3部作(前編、中編、後編)に分けて
ご紹介させてくださいね。
前編
身延町から早川町へ入り、県道37号線一般車両が行ける終着地点までを目指し、途中の吊り橋、西山ダムをご紹介

中編
早川町の奥地にある秘境奈良田の里。
七不思議伝説の軌跡をたどりながら、源泉かけ流し温泉、地元のジビエを堪能しながら里を一周してきたのでおすすめの見どころをご紹介
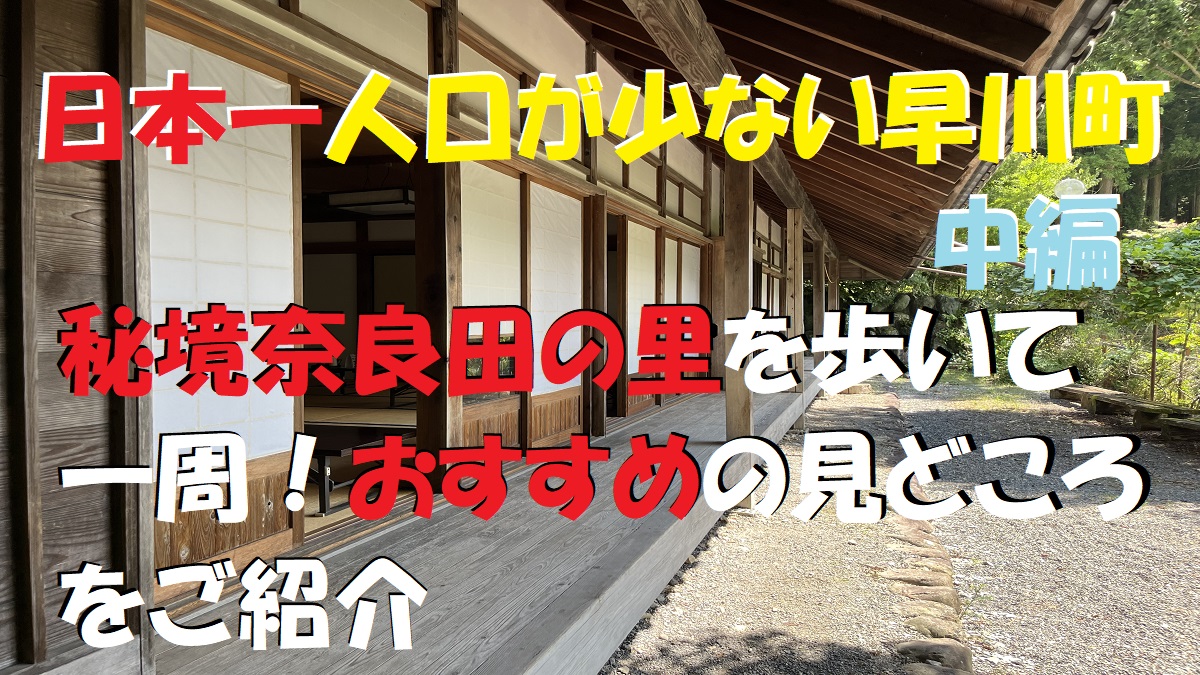
後編
奈良田の里から県道37号線を南下し、途中にある茂倉の集落、昭和当時の建物が現存するノスタルジックな街並みの赤沢宿をご紹介
南アルプス市-帰りの南アルプスプラザ
田んぼのあぜ道を南下
8:15
国道52号線を南下
8:30
8:55
9:30
9:50
10:05
10:30
13:30
14:05
14:45
15:25
中編の続き
奈良田の里散策を終え、県道37号線を南下する形で茂倉の集落方面へ向かいます。
奈良田の里で温泉でゆっくり旅の疲れをとり、食事で疲れた体にエネルギーを注入したところで
奈良田の里を後にします。
奈良田の里 出発
ひたすら県道37号線を南下し、途中の西山温泉、湯島の大杉を通り過ぎ、およそ25分で茂倉の集落への入口新倉の集落に到着。

(画像は新倉集落バス停前で撮影)
新倉の集落の目印は、手前に水力発電所があるのでわかりやすいと思います。
こちらの写真は、南側の南アルプスプラザ方面からくるとある新倉(あらくら)の集落入口の看板。

(画像は県道37号線から入る新倉、茂倉集落入口で撮影)
目的地の茂倉の集落は山間の奥深くにあるため、麓にある新倉の集落から山道を通る必要があります。
茂倉の集落へ続く山道入口の目印は三里郵便局!
集落の中ではよく目立つので、迷わないと思いますよ。

(画像は三里郵便局前で撮影)
そして、三里郵便局向かい側にある茂倉入口の案内板。
早速山道をバイクで登って行きたいと思います。

(画像は新倉集落内にある茂倉方面の入り口で撮影)
山道は細く大型な車はすれ違い困難かな。
所々に路側帯があり、そこで車はすれ違いするみたい。

(画像は茂倉集落へ向かう細い山道で撮影)
くねくねと山道を走る事10分程で着きました。

(画像は茂倉集落へ向かう杉林の山道で撮影)
茂倉(もぐら)の集落

(画像は茂倉集落で撮影)
かつては身延町方面から十谷峠を越えて、新倉集落へと水力発電建設工事に従事する人が往来していたみたいでしたが、現在は十谷峠方面は車両通行止めで、人の行き来がほとんどなく山間に孤立した形で残っているみたいです。
現在は少数の人しか住んでおらず、人が住んでいる家屋より人が住んで居ない家屋の方が多いみたいで集落は静まり返っていました。
そんな中、最初に集落の一番高台にある七面宮へ向かいます。
集落の真ん中に少し広めな道路があるので真っ直ぐ進み、集落の端から登る様に道路を走ります。
七面宮

(画像は七面宮で撮影)
赤い入母屋屋根が特徴の七面宮に着きました。
入口にある大きな杉の木があり、その奥には立派な拝殿があります。
参拝を済まし、ここからは茂倉を歩いて散策してみたいと思います。

(画像は七面宮正面入口で撮影)
高台からみた茂倉
急勾配の山間にあるのが分かります。周りの山間の木々がもりもりしていて、山深いところにある事が確認できますよ。

(画像は茂倉集落で撮影)
獣用の箱罠
中にはトウモロコなどがあり、いのしし🐗とかの獣を捕まえるのかな。
これも集落では貴重なタンパク源。

(画像は茂倉集落内にある獣用の箱罠前で撮影)
道は集落の真ん中の道以外は狭く、軽トラがギリギリ通れるか通れないかぐらいの道幅しかなく散策するなら歩いて行くしかなさそう。
この急勾配の道。山の急斜面にある事が分かります。

(画像は茂倉集落で撮影)
昔のトタン看板
現代では地方でし見かけないかな。
旧字体が使われているので、戦前ぐらいの時期に作られたみたいですよ。

(画像は茂倉集落で撮影)
道路側ギリギリに建てられている家屋。
時代を感じます。

(画像は茂倉集落で撮影)
真っ赤な鳥居が見えてきました。
國玉神社

(画像は國玉神社で撮影)
集落にはない色の鮮やかな赤色が使われていて、一際目立つ存在。
奥にはコンクリート製の社殿がありここで参拝できそうです。
狛犬の前にある奉納が平成5年と書いてあり、以前は違う形で鎮座していたことが分かります。

(画像は國玉神社で撮影)
同じ境内にある、安楽山西方寺。
神社とお寺が同じ境内にあります。

(画像は安楽山西方寺で撮影)
ここまで集落を散策しましたが、驚くほど人の声、気配はなく誰もいないんではないかと思うぐらい静かな集落。
散策を終わりにして七面宮へと戻り、茂倉の集落を後にしたいと思います。
来た時と同じ道を戻る形で、麓の新倉集落にある三里郵便局へ戻りました。
ここで少し気になったんですが、新倉集落にあるので何で三里郵便局?
調べていると、、、
この辺りは旧三里地区に分類されているみたいで、
早川(ハヤカワ)
大原野(オハラノ)
塩島(ショジマ)
柿草里(カキゾウリ)
中州(ナカス)
新倉(アラクラ)
茂倉(モグラ)
以上の七つの集落からなってっています。
地名の由来、詳細は早川町公式ホームページで確認してみてくださいね。
※外部サイトへリンク早川町公式ホームページ
ここから県道37号線を南下する形で南アルプスプラザ方面へ向かいます。
南アルプスプラザ 到着

(画像は南アルプスプラザ前で撮影)
新倉集落から25分程で到着。
現時刻が15時30分頃で一日で観光できる限界の時間かな。
本来ならば一日で赤沢宿まで行きたいところですが、別日に観光した赤沢宿のご紹介をしたいと思います。
赤沢宿へは、南アルプスプラザから県道37号線を外れ春木川沿の山道を南下します。
春木川沿いの道は2本に分かれていて、
川沿いは七面山登山口方面へ
山間は赤沢宿方面に分かれています。
地図で見ると分かりやすいですが、赤沢宿方面の道は山間になります。
近隣の登山

因みに写真はないですが、赤沢宿方面へ登る山道は先ほどご紹介した茂倉集落へ続く山道より狭く細いです。
多分普通自動車では行くにはそれなりの覚悟が必要かと思われます。
赤沢宿

(画像は赤沢宿石碑前で撮影)
西側に七面山、東側に身延山に挟まれていている宿場町でした。
江戸時代に入ると七面山登山の女人禁制が解かれ、さらに入山客も増え、当時は旅籠としても活気があったとされています。その後、明治、大正、昭和頃まで身延線の開通とともに参拝客が急増して、たいそうな賑わいを見せたみたいです。
しかしながら、現在は迂回路などの交通の便が発達してきてわずかな宿場等を残し現在に至ります。
ここも茂倉集落同様に細い山道を登った先にある山間の集落。
広さ地形も似ていて、集落全体が山間にある。
集落の最上部付近に位置する妙福寺から、下りながら散策したいと思います。
以前は賑わいを見せていたであろう町並み。
石畳の坂道は風情があって集落全体の雰囲気タイムスリップしたような感覚。

(画像は赤沢宿で撮影)
喜久屋 歴史文化公園休憩処

(画像は赤沢宿にある喜久屋正面入口で撮影)
休憩処屋内に厠あり
賑わいを見せていた当時の旅籠屋跡。
現在では休憩所として利用されています。
木造二階建てで一階には囲炉裏、2階は畳部屋の2間になっていて、現在も綺麗に管理されています。

(画像は赤沢宿にある喜久屋室内2階で撮影)
囲炉裏の部屋の天井は煤で黒く当時の生活が分かります。

(画像は赤沢宿にある喜久屋室内1階で撮影)
旅館 大黒屋

(画像は赤沢宿にある大黒屋正面入口で撮影)
小さい看板が軒下にズラリと並んでいます。この看板の名称ってあるんですかね?
今はあまり見かけませんが、旅館などの入口にある歓迎看板〇〇様みたいな意味合いでしょうか?
分かる方がいましたら、ぜひコメント欄で教えて下さると助かります💦

(画像は赤沢宿にある大黒屋正面入口で撮影)
赤沢宿 公民館

(画像は赤沢宿にある公民館正面入口で撮影)
木造平屋建ての公民館。
車を1~2台ほど駐車できます。
赤沢宿には実際に営業しているお店(お蕎麦屋さん、カフェ)があるのですが、
今回は時間の関係でお邪魔できませんでした;つД`)
次回観光に来た際には行ってみようと思います。
清水屋 カフェ
ゆるキャン△聖地巡礼としても有名。
リンちゃんも食べた地元産を使った豆もちなど、休憩処としても利用してみてはどうでしょうか。
武蔵屋 そば処
天ぷら、そばなど地元の食材を使った人気店。赤沢宿の唯一の食事処。
細く急勾配な石畳の坂道
昔の雰囲気を残す宿場町を歩くと当時の賑わいを見せた情景が浮かぶようです。

(画像は赤沢宿にある細く急勾配な石畳の坂道で撮影)
帰りは石畳を登り集落の上部にある妙福寺まで戻ります。
今回の赤沢宿散策はここまでにします。


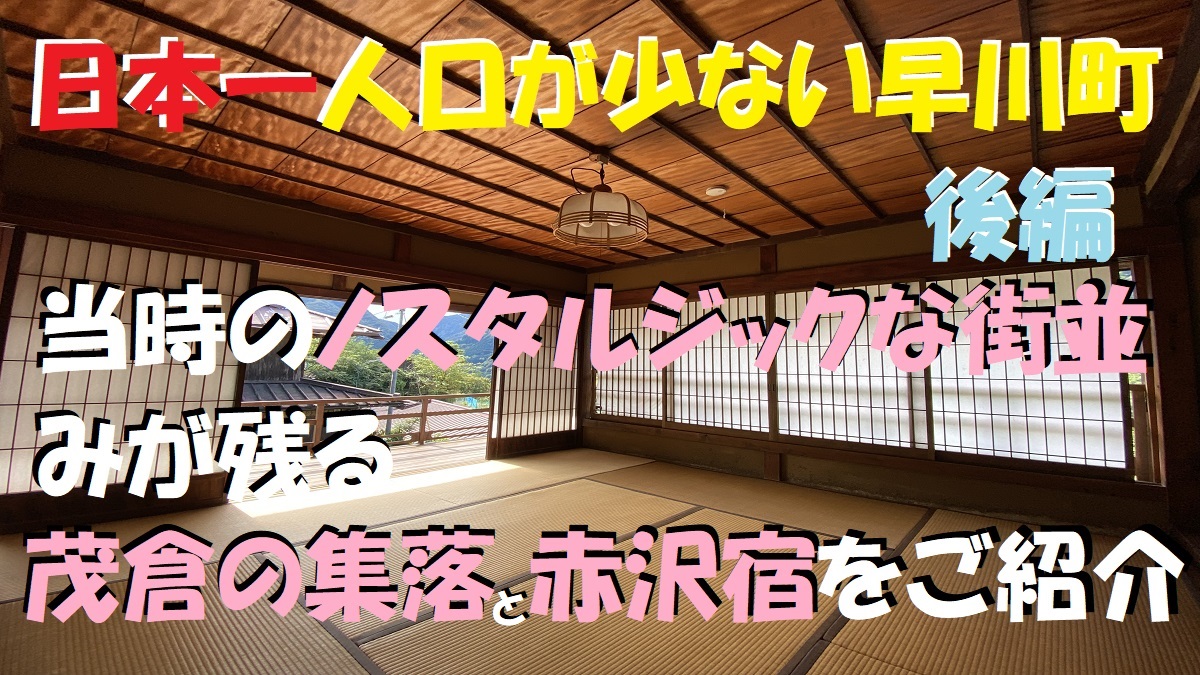



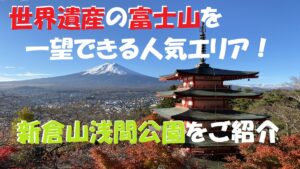
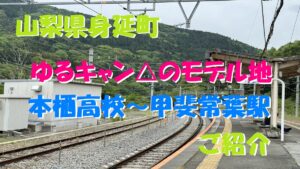





コメント
コメント一覧 (4件)
[…] 日本一人口が少ない早川町 【後編】当時のノスタルジックな街並みが残る… […]
[…] 日本一人口が少ない早川町 【後編】当時のノスタルジックな街並みが残る… […]
サイトのナビ 誠実 — 必要な情報がすぐ見つかる。
本みたいに面白い。本当にありがとう!で やる気もらえます。 [url=https://iqvel.com/ja/a/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%A7%E5%9F%8E]トゥルイユの塔[/url] 珍スポット この地図解説で ポイント抑えやすい。